防穀令事件の朝鮮側の主張と日本側の主張【歴史部生徒質問・調べてみた】
- 順大 古川
- 2025年8月20日
- 読了時間: 4分
個人レベルで調べて勉強しているので、誤りもあるかと思います。事実誤認や参考文献の読み間違いなどがありましたら、ご教示いただけるとありがたいです。
【生徒さん質問】
防穀令事件の朝鮮側の主張と日本側の主張は?
回答:
まず、国史大辞典で防穀令事件を確認しておきます。
日朝修好条規締結(明治九年(一八七六))後とみに盛んになった日本商人による穀物(米・大豆)の対日輸出を、朝鮮側が阻止しようとしたことから発生した日朝間の紛争事件。防穀とは元来、李朝時代、朝鮮で地方官が、自己の行政管轄内で凶作・兵乱などによる穀価の騰貴を防止するため、穀物売買・運搬の禁止、購入穀物の差し押えなどを行うことをいう。日本との貿易開始後、余剰農産物でもない米・大豆の日本商人による日本への大量輸出が始まり、穀価が騰貴し、防穀は朝鮮の支配層にとって欠くべからざる政策となった。したがって、明治十六年七月に調印された「朝鮮国に於て日本人民貿易の規則」第三十七款では、朝鮮の地方官が一ヵ月前に日本領事官に予告して防穀を行うことができるのを認めていた。防穀令は、一八八四年から一九〇一年の間に二十七件を数える。その中、明治二十二年五月、黄海道観察使趙秉轍、同年十月から翌年五月にかけて咸鏡道観察使趙秉式、同二十三年三月、黄海道観察使呉俊泳が発令した三件の防穀令は、それぞれ居留地日本商人がその解除を求め、朝鮮政府に賠償請求を行い、紛争が日本と朝鮮の外交問題に発展した点で著名である。三件ともそのつど、在朝鮮の日本外交官が朝鮮政府に抗議し、その撤回や当該地方官の処罰などを求め、事態は落着したものの、日本商人は日本政府を動かし、政府もまた初期議会の対外強硬論に対処するため、明治二十四年十二月、改めて梶山鼎介公使をして十四万七千余円の損害を朝鮮政府に請求、重大な紛争に発展した。交渉は難航し、翌年第二次伊藤内閣は外相陸奥宗光の指導のもと、自由党員大石正己を公使に起用、新たに要償額を十七万余円にして強硬姿勢をとり、これに応じない朝鮮政府に対し、外交断絶までほのめかし、裏面で清国の李鴻章に斡旋を依頼し、ようやく明治二十六年五月、賠償金十一万円で妥結した。
上の赤字の部分が、テキストにあった防穀令事件です。
そんで、歴史部のなかで国史大辞典を確認したときに、予告がなされてなかったりしてこじれたのかもしれませんね、といったことを話しました。
それで、吉野誠氏の論考を読んでみました。
吉野氏によると、国史大辞典の該当記事を書いた唐沢たけ子氏などの先行研究によると、防穀令の予告から実施までに一ヶ月なかったことが問題だと日本側が主張したと言われているそうです。
しかし、吉野氏は史料にある「十月底」の語の解釈などをもとに、防穀令の予告から実施までは1ヶ月の期間をとって条約を遵守しており、日本側もこの期間を問題していなかったことを指摘しました。
そして、日本側は朝鮮が防穀令を出すときに、日本の同意を得なかったことを主に問題としたとします。
なお、朝鮮側の主張は、今回は日本の同意を必要としないケースであり、防穀令の対象も朝鮮人間の取引であるから問題ないはずだといったものでした。
防穀令事件については、上記の吉野誠氏のものが新しくて詳しいので、調べるときは吉野氏の論文にあたって、必要に応じて唐沢氏の論考も確認するといいと思います。
吉野氏の論文は1と2はwebで見られたのですが、3はまだweb上では公開されていなかったので、見れてません。今回のテーマについては1だけ読めば大丈夫です。
参考文献:
(3,吉野誠「防穀令事件の外交交渉ー最後通告から妥結までー」(『東海大学文学部紀要』・2013年)
(4,唐沢たけ子「防穀令事件」(『朝鮮史研究会論文集』六))


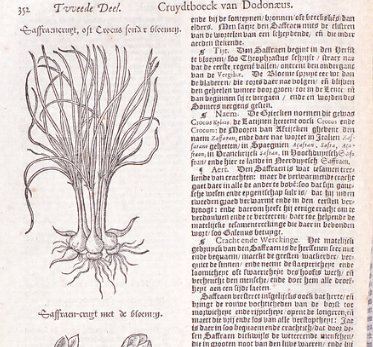

コメント