大友氏と大村氏【歴史部生徒質問・調べてみた】
- 順大 古川
- 2025年8月6日
- 読了時間: 2分
個人レベルで調べて勉強しているので、誤りもあるかと思います。事実誤認や参考文献の読み間違いなどがありましたら、ご教示いただけるとありがたいです。
【生徒さん質問】
戦国・安土桃山時代の大友氏と大村氏と有馬氏の同盟関係。
回答:
まず可能な限り雑に北部九州の戦国大名の盛衰をみておくと。
大内義隆が陶晴賢に敗れる(厳島の戦い・1555年)
→大内氏の勢力が後退して大友氏の勢力が強くなる
→大友宗麟が島津に負ける(耳川の戦い・1578年)
→龍造寺隆信の勢力が強くなる
→龍造寺隆信が島津に負ける(沖田畷の戦い・1584年)
→大友が少し復活して島津が強くなるけど、豊臣秀吉が入ってきて九州勢力は一掃される
ってな感じです。
大友宗麟は九州のトップ争いに絡んでくる九州ティア1大名ですが、有馬はティア2で、大村はティア3の大名となります。
断片的になりますが、
大村純忠は有馬氏からの養子で、有馬晴信の叔父にあたります。有馬氏と大村氏は密接な同盟関係にありました。大村氏のほうが格下です。また、大友と大内が争っていたころは、有馬氏は大友側につくことが多かったようです。1560年代の有馬氏は、龍造寺氏に対抗するために大友氏をよく頼っていました。
1570年、大友宗麟が龍造寺隆信を攻めたときは、有馬氏は龍造寺氏側についています。
1576年、有馬氏の傘下にあった大村純忠が、龍造寺隆信の傘下に入ります。
1579年、大村純忠が龍造寺氏の傘下に入ります。
1582年、有馬氏は龍造寺氏から離反して、島津氏に支援を要請します。
1583年、島津氏が助けてくれなかったので、有馬氏は龍造寺氏に降伏して、龍造寺配下に戻ります。ただ、有馬氏はまだ島津氏に手紙を送ったり、大友氏に援軍を要請したりしています。
1584年、島津氏が本格的に龍造寺氏を攻めて滅ぼしたときは、有馬氏はガッツリと島津側についています。
有馬とその親戚の大村は龍造寺よりも西にいて、龍造寺氏が強くなったあとは大友との関係はそこまで深くなったことはないようです。1582年の天正遣欧使節のときも、大村純忠と大友は事前協議していないそうです(『戦国武将列伝11 九州編』)。
参考文献:


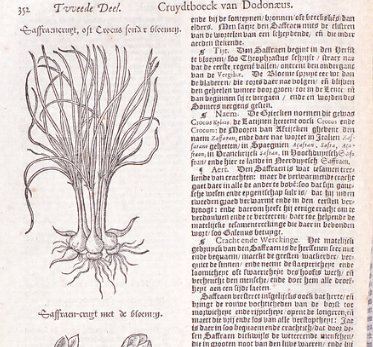

コメント